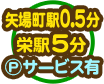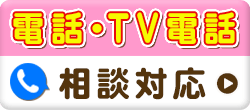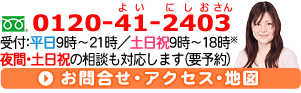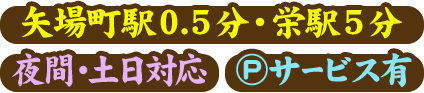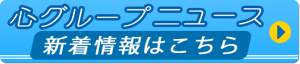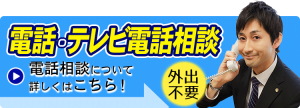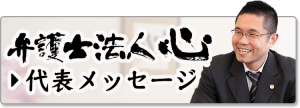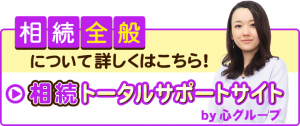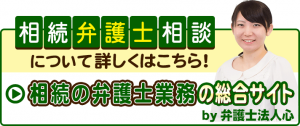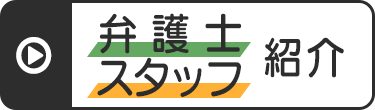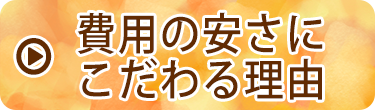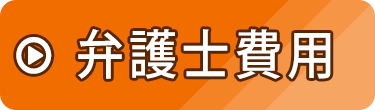相続放棄後にしてはいけないことに関するQ&A
Q相続放棄後にしてはいけないことというのはありますか?
A
相続放棄後にしてはいけないことについては、民法921条3号に定められています。
具体的には、次のような条文が存在します。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 (省略)
2 (省略)
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
条文を分けてみますと、相続放棄後に、
①相続財産の全部若しくは一部を隠匿すること
②私にこれを消費することをしてしまうこと
をすると、単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄が無効になるとされています。
また、民法921条第3号には、「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」という要件も記載されています。
ただし、これは限定承認をした場合のことですので、相続放棄にはあてはまりません。
Q「相続財産の全部若しくは一部を隠匿すること」とはどういったことですか?
A
相続財産の隠匿とは、その相続財産の所在を不明にする行為のことをいいます。
例えば、相続財産である現金を持ち去って、他の人にはわからない場所に移してしまうような行為が挙げられます。
この行為が禁止される理由は、次のようなものであると考えられます。
まず、相続人全員が相続放棄をすると、相続人がいなくなります。
被相続人に債務があった場合、被相続人の債権者が相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産から債権の回収をする可能性があります。
このとき、もし相続放棄をした元相続人が相続財産を隠匿してしまうと、被相続人の債権者による債権回収を妨げることとなり、実質的に債権者に損害を発生させてしまうことになります。
なお、財産価値のない遺品の形見分け程度であれは、隠匿に該当しないとされています。
しかし、中にはどの程度であれば隠匿にあたるのかの判断が難しいケースもあります。
相続放棄した後の形見分けについて迷った際は、弁護士に相談することをおすすめします。
ちなみに、相続放棄前の形見分けや遺品整理は法定単純事由に該当するおそれがあり、相続放棄が認められなくなるケースもあります。